【最新情報】アスクル・LOHACOの受注・出荷停止の現状と再開時期は?
アスクル・LOHACOのシステム障害発生日時と最新の復旧状況
「えっ、LOHACOで注文できない!」「会社のアスクルが開かない!」
2025年10月19日の日曜日、多くの方がそんなパニックに見舞われたのではないでしょうか。
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という衝撃的な事態は、2025年10月19日(日)の午前中に発生が検知されました。
アスクル株式会社からの公式発表によると、原因は「ランサムウェア」と呼ばれる非常に悪質なコンピュータウイルスへの感染です。
ランサムウェアというのは、ひと言でいうと「身代金要求型ウイルス」のこと。
会社のシステムやデータを勝手に暗号化して使えなくしてしまい、「元に戻してほしければ身代金を払え」と脅迫してくる、本当に卑劣なサイバー攻撃なんです。
この攻撃を受けた結果、アスクルおよびLOHACOの心臓部ともいえる物流や受注のシステムが停止してしまいました。
「じゃあ、いつになったら復旧するの?」「明日のトイレットペーパー、注文してたのに!」
皆さんが今一番知りたい「復旧時期」についてですが、2025年10月20日(月)早朝の時点でも、残念ながら「復旧のめどは立っていない」というのが公式な状況です。
公式サイトでは「一刻も早いシステムの復旧に向けた対応を行っております。復旧のめどが立ち次第、改めてお知らせいたします」と発表されていますが、具体的な日時はまだ示されていません。
「明日届くはずだったのに…」と肩を落としている方も多いかと思いますが、今はアスクル・LOHACOの技術者さんたちが不眠不休で対応してくれていると信じて、公式からの続報を待つしかない状況です。
このアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の問題、本当に影響が大きすぎますよね…。
私たち消費者ももちろんですが、オフィスで「明日使うコピー用紙がない!」と困っている事務の方もたくさんいらっしゃるはずです。
まずは、現在システムが完全に停止しているという事実を受け止め、代替手段の確保を急ぐ必要がありそうです。
受注停止の影響範囲:法人向けASKULと個人向けLOHACOの違い
「うちは会社でASKULを使ってるんだけど、影響は?」「私は個人でLOHACOを使ってるんだけど、こっちもダメなの?」
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の問題、その影響範囲は非常に広く、残念ながら法人向けサービスも個人向けサービスも両方ともストップしてしまっています。
「どっちかは動いているかも…」と淡い期待を抱いてしまいますが、現実はかなり厳しいようです。
具体的に、それぞれのサービスで「何ができて、何ができないのか」を整理してみました。
【影響範囲の比較】
| サービス名 | 主な対象 | 停止している主な業務 |
|---|---|---|
| ASKUL (アスクル)
ソロエルアリーナ |
法人・個人事業主 | 受注・出荷業務
Webサイトの一部機能(お買い物カゴ、レジ画面など) 返品・各種回収サービス カタログの申込み |
| LOHACO (ロハコ) | 個人向け | 受注・出荷業務
(サイトは閲覧できても注文が完了できない状態) |
ご覧の通り、どちらのサービスも「受注(注文の受付)」と「出荷(商品の発送)」という物流の根幹が完全に停止してしまっています。
特に法人向けのASKULやソロエルアリーナでは、影響がさらに深刻です。
公式サイトの情報によると、注文や出荷だけでなく、「返品の申し込み」や「使用済みトナーの回収サービス」、「カタログの請求」といった付帯サービスも軒並み停止しているとのこと。
サイトにアクセスしても、「お買い物カゴ」や「レジ」の画面に進もうとするとエラーになってしまう、という報告も相次いでいます。
「週末に注文だけ入れておこう」と思っていた企業の担当者さんは、月曜の朝から頭を抱えているかもしれませんね…。
個人向けのLOHACOも状況は同じです。
「サイトは見られるけど、いざ注文しようとすると進めない」「カートに入らない」といった状態で、実質的に買い物が一切できない状態となっています。
結論として、ASKULもLOHACOも、現時点ではサービス利用の再開ができない状態であり、その影響は全ユーザーに及んでいる、というのが現状です。
再開時期の予測:公式発表と専門家の推測
さて、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の問題で、私たち利用者が一番知りたいこと。
それは、「一体、いつになったら再開するの?」ということに尽きますよね。
まず、アスクル株式会社からの「公式発表」を見てみましょう。
2025年10月20日(月)早朝の時点での発表では、「復旧のめどは立っておりません」とされています。
「現在、一刻も早いシステムの復旧に向けた対応を行っております。復旧のめどが立ち次第、改めてお知らせいたします」とのこと。
「今日中?」「今週中?」と具体的なスケジュールが知りたいところですが、残念ながら公式からは「未定」としか言えない、というのが正直なところのようです。
では、なぜこんなに時間がかかっているのでしょうか?
ここで「専門家の推測」…というか、一般的なランサムウェア被害からの復旧プロセスについて少し触れておきますね。
今回の原因は、ただのシステムエラーではなく「ランサムウェア」というサイバー攻撃です。
この場合、復旧作業は簡単なものではありません。
1. フォレンジック(被害状況の調査)
まず、「どこから侵入されたのか?」「どの範囲までウイルスが広がっているのか?」「データは盗まれたのか?」を徹底的に調査する必要があります。これを「フォレンジック」と呼びます。
2. システムの隔離と駆除
これ以上被害が広がらないよう、感染したシステムをネットワークから切り離し、ウイルスを完全に駆除します。
3. システムの復旧・再構築
ウイルスに暗号化されてしまったデータを、安全なバックアップから元に戻す作業(リストア)を行います。もしバックアップまで被害が及んでいたら、システムを一から作り直す必要さえ出てきます。
4. 安全確認と再発防止
本当に安全か、侵入された穴(脆弱性)は塞がっているかを何度も確認し、対策を施してから、ようやくサービス再開となります。
…どうでしょう?これだけの作業を、あの大規模なASKULとLOHACOのシステム全体で行うとなると、数時間や1日で終わる可能性は極めて低い、というのが専門的な見方です。
過去の他社の事例を見ても、ランサムウェア被害からの完全復旧には、短くても数日、長い場合は数週間から1ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。
「明日の朝には直ってるかも」と期待したい気持ちは山々ですが、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の問題については、少し長期戦になる可能性も覚悟して、代替の購入先などを探しておくのが賢明かもしれませんね。
【参照】
個人情報流出の可能性と調査進捗
「アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止」のニュースを聞いて、システムが止まっている不便さと同じくらい…いえ、それ以上に心配なのが、
「私の個人情報、大丈夫!?」
ということですよね。
LOHACOやASKULには、私たちの氏名、住所、電話番号、会社名、そして過去の購入履歴など、大切な個人情報がたくさん登録されています。
「クレジットカード情報まで盗まれちゃったんじゃ…」と想像すると、本当に生きた心地がしません。
まず、この点に関するアスクル株式会社の「公式発表」を確認しましょう。
2025年10月19日の第1報によると、「個人情報や顧客データなどの外部への流出を含めた影響範囲については現在調査を進めており、わかり次第お知らせいたします」とあります。
…つまり、2025年10月20日(月)早朝の時点では、「流出したかどうかも含めて、まだわかっていません(調査中です)」というのが公式な回答です。
「漏れてないなら『漏れてない』って言ってほしい!」と思いますが、そう言えないところに、今回のランサムウェア攻撃の厄介さがあります。
最近のランサムウェア攻撃は、ただデータを暗号化する(使えなくする)だけじゃないんです。
攻撃者はデータを暗号化する「前」に、まず企業のサーバーからこっそり顧客情報や機密データを盗み出します。
そして、「身代金を払わなければ、盗んだこの個人情報(や会社の秘密)をインターネット上に全部バラまくぞ」と脅迫してくるのです。
これを「二重脅迫(ダブルエクストーション)」と呼びます。
だからこそ、アスクル側も「データが盗まれた可能性」を最優先で調査しているはずなんです。
現時点では、「個人情報が流出した」という事実は確認されていませんが、同時に「流出していない」とも断言できない、非常にグレーな状況です。
(ちなみに、過去にアスクルでは2021年や2024年にも、委託先の不正アクセスなどで個人情報が流出した可能性が発表されたことがありましたが、今回はそれらとは全く別の、本社システムそのものへの直接攻撃とみられます。)
クレジットカード情報については、一般的にECサイトではカード番号そのものをサーバーに保存せず、決済代行会社のシステムを使っていることが多いです。
そのため、カード情報がごっそり盗まれるリスクは比較的低いかもしれませんが、こればかりは公式の調査結果を待つしかありません。
私たちにできることは、不審なメール(アスクルやLOHACOを装ったフィッシング詐欺など)に絶対に注意すること、そして公式発表を冷静に待つことですね。
出荷済み商品の対応とキャンセル対象の詳細
「昨日LOHACOで注文したんだけど、あれってどうなるの?」
「会社のASKULで大量に発注かけた直後だった…。届かないの!?」
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の騒動で、復旧時期や個人情報と並んで、最も混乱しているのが「すでに注文した商品の行方」ですよね。
楽しみに待っていた商品、あるいは業務で必須の備品がどうなるのか…。
この点について、アスクル株式会社は第1報で、非常に重要な発表をしています。
それは、「すでにいただいたご注文については、大変恐れ入りますがご注文キャンセルとさせていただきます」という一文です。
…えっ、キャンセル!?
そうなんです。システムが停止してしまったため、受注データが物流センターに正常に渡せず、出荷作業そのものができなくなってしまったんですね。
そのため、障害発生(10月19日)より前に注文が完了していたとしても、「まだ出荷作業に入っていなかった(未出荷の)」注文については、すべて強制的にキャンセル扱いとなる模様です。
「注文確定メールが来てたのに!」と思っても、システムが動かない以上、発送しようがない…という苦渋の決断だったのだと推測されます。
では、ここで一つの疑問が浮かびます。
「じゃあ、『出荷済み』のものはどうなるの?」
障害発生より前にすでに「発送完了メール」が届いている商品や、アスクルロジストなどの配送業者がすでに荷物を預かっている「出荷済み」の商品についてです。
この「出荷済み商品」の対応については、現時点の公式発表では明確に言及されていません。
ここからは推測になりますが、
パターン1:無事に届く
すでにアスクルの倉庫から出て、配送業者の手に渡っている荷物については、そのまま配送が継続され、手元に届く可能性が高いです。
パターン2:配送もストップする
ただし、配送業者のシステムとアスクルのシステムが連携している場合、障害の影響で配送情報が追跡できなくなったり、万が一のことを考えて配送が一時停止されたりする可能性もゼロではありません。
「発送完了メールは来たけど、荷物追跡ができない」といった事態が起こるかもしれません。
結論として、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の影響により、
・【未出荷のご注文】 → 原則すべて強制キャンセル(再開後に再注文が必要)
・【出荷済みのご注文】 → 届く可能性が高いが、詳細は公式発表待ち
ということになりそうです。
キャンセル分の返金処理なども含め、まだまだ混乱は続きそうですね…
ランサムウェア感染はなぜ起こった?システムへの侵入経路と背景を解説!
ランサムウェアの種類とアスクルへの攻撃手法
さて、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という大変な事態を引き起こした犯人、「ランサムウェア」。
名前は聞いたことがあるかもしれませんが、一体どんなものなのでしょうか?
ひと言でいえば、これは「身代金要求型ウイルス」です。
パソコンや会社のシステムに入り込んで、大切なデータファイル(顧客情報や在庫データなど)を勝手に暗号化して開けなくしてしまうんです。
そして、「データを元に戻してほしければ、身代金(主にビットコインなどの暗号資産)を払え」と脅迫してくる、とっても悪質なサイバー攻撃なんですね。
今回のアスクルへの攻撃が、具体的にどのグループ(例えば「LockBit」や「BlackCat」といった有名な攻撃者集団がいます)によるものか、どんな種類のランサムウェアが使われたのかは、現時点(2025年10月20日)ではまだ公式に特定されていません。
しかし、近年のランサムウェア攻撃のトレンドとして、ただデータを暗号化するだけでは終わらない、さらにたちの悪い手口が主流になっています。
それが「二重脅迫(ダブルエクストーション)」と呼ばれる手法です。
これは、データを暗号化する「前」に、まず企業のサーバーからこっそり機密データや個人情報を盗み出しておくんです。
そして、「身代金を払わなければ、盗んだこの個人情報をダークウェブ(闇のインターネット)で公開するぞ」と、二重に脅迫してくるわけです。
私たちが「個人情報の流出は大丈夫!?」と真っ先に心配したのも、まさにこの手口が一般的になっているからなんですね。
アスクルのような巨大な物流システムが完全に停止したことからも、今回の攻撃は単なるデータ暗号化にとどまらず、システムの中枢(心臓部)まで深く侵入し、業務継続そのものを破壊する、非常に強力な攻撃だったと推測されます。
だからこそ、復旧に時間がかかってしまっているんですね…。
侵入経路の可能性:フィッシングメールや脆弱性悪用
「そもそも、なんでアスクルみたいな大企業が、そんなウイルスに入られちゃったの?」
本当にそう思いますよね。アスクルほどの会社なら、厳重なセキュリティ対策をしていたはずです。
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止問題で、犯人がどうやってシステム内部に忍び込んだのか、その「侵入経路」についても、まだ公式な特定には至っていません。
しかし、こうしたサイバー攻撃の「入口」となる手口は、だいたいパターンが決まっています。
専門家の間で、最も可能性が高いとみられているのは、大きく分けて次の2つです。
1. フィッシングメール(巧妙な偽メール)
これが最も古典的で、今なお最も多い侵入経路です。
「え?いまどき怪しいメールなんて開かないよ」と思うかもしれません。
でも、最近のフィッシングメールは本当に巧妙なんです。
実在する取引先や配送業者、あるいは行政機関などを装い、「【緊急】請求書の内容ご確認」「配送情報の不備について」といった、思わず開いてしまいそうな件名で送られてきます。
そのメールに添付されたファイル(WordやExcel、PDFに見せかけたもの)を開いたり、本文中のリンクをクリックしたりした瞬間、ウイルスがパソコンに侵入してしまうのです。
アスクルのような多くの取引先とメールをやり取りする企業では、従業員の誰か一人がうっかり騙されてしまうだけで、それが侵入の突破口になり得ます。
2. 脆弱性(ぜいじゃくせい)の悪用
ちょっと難しい言葉が出てきましたね。「脆弱性」というのは、ひと言でいえば「ソフトウェアや機器のセキュリティ上の弱点・穴」のことです。
特に狙われやすいのが、「VPN機器」です。
VPNというのは、社員が自宅や出張先からでも、安全に社内のネットワークに接続(リモートワーク)するための装置のこと。
このVPN機器に古いバージョンの穴(脆弱性)が残っていると、攻撃者はそこを狙って、まるで正社員になりすましたかのように堂々と社内ネットワークに侵入できてしまうんです。
2025年のサイバー攻撃のトレンドとしても、このVPNやリモートデスクトップ(遠隔操作)の脆弱性を狙った攻撃が非常に増えていると報告されています。
アスクルがどちらの経路でやられてしまったのかは調査結果を待つしかありませんが、攻撃者は常にこうした「人間のうっかり」や「システムの穴」を探している、ということですね。
アスクルのセキュリティ体制と過去の対策の検証
「これだけの大被害が出たってことは、アスクルのセキュリティ体制、ガバガバだったんじゃないの?」
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という結果だけを見ると、ついそう思ってしまいますよね。
もちろん、結果としてあれだけの大規模なシステム停止と受注停止に陥ってしまったわけですから、セキュリティ体制のどこかに「隙」や「想定の甘さ」があったことは間違いありません。
しかし、アスクルほどの大企業が、何の対策もしていなかったとは考えにくいです。
例えば、アスクルは情報セキュリティ管理の国際規格である「ISMS認証(情報セキュリティマネジメントシステム)」を2005年というかなり早い段階で取得しています。
これは、会社として「情報をちゃんと管理する仕組みを作っていますよ」という国際的なお墨付きのようなものです。
当然、ウイルス対策ソフトの導入、ファイアウォール(不正な通信を防ぐ防火壁)の設置、社員へのセキュリティ教育など、一般的な対策は行っていたはずです。
では、なぜ防げなかったのでしょうか?
ここからは推測になりますが、いくつかの可能性が考えられます。
1. 「防御」をすり抜ける最新の手口だった
先ほどお話しした侵入経路のように、従来のウイルス対策ソフトでは検知できない、まったく新しい手口の攻撃(ゼロデイ攻撃)だった可能性です。これだと、どんなに万全に対策していても、最初の侵入を防ぐのは非常に困難です。
2. 「検知」と「対応」の遅れ
侵入された後の「あれ?何かおかしいぞ」と気づく(検知する)体制や、気づいた後に「すぐに犯人を叩き出す(対応する)」仕組みが、攻撃者のスピードに追いつかなかった可能性です。特に日曜日の午前中という、システム管理者の監視が手薄になりがちな時間帯を狙われた可能性も否めません。
3. バックアップシステムへの被害
これが最悪のシナリオですが、ランサムウェア攻撃者は、データを暗号化するだけでなく、データを元に戻すための「バックアップ」まで狙って破壊しにきます。
もし、アスクルが持っていたバックアップデータまで暗号化されたり、アクセス不能にされたりしていた場合、システムの復旧は絶望的に困難になります。
「復旧のめどが立たない」という公式発表が続いている背景には、もしかしたらこのバックアップからの復旧がうまくいっていない…という深刻な事態があるのかもしれません。
今回の被害は、「完璧なセキュリティは存在しない」という現実と、侵入された後(・・・・・)にいかに早く検知し、いかに安全なバックアップから復旧できるか、という「被害軽減(レジリエンス)」の重要性を改めて突きつける形となりました。
【参照】
業界全体のランサムウェア脅威増加の背景
「それにしても最近、こういうサイバー攻撃のニュース、多くない?」
そう感じている方、その感覚は非常に正しいです。
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止は、決して他人事ではなく、日本全体、いや世界中の企業が直面している「脅威」が、たまたまアスクルという形で表面化したにすぎません。
なぜ、こんなにもランサムウェア攻撃が増え続けているのでしょうか?
その背景には、攻撃が「非常に儲かるビジネス」として完全に産業化してしまった、という恐ろしい現実があります。
1. RaaS(ラース:Ransomware as a Service)の普及
「RaaS」…なんだか「SaaS(サース:Software as a Service)」みたいですよね。
その通りで、これは「ランサムウェア攻撃の代行サービス」なんです。
昔は、高度な技術を持ったハッカー集団しか、大企業への攻撃はできませんでした。
しかし今は違います。
攻撃の「プロ」が、ウイルスや攻撃ツール、脅迫文のテンプレートまで全部パッケージにして、「誰でも簡単に攻撃できますよ」と闇サイトで販売しているんです。
まるでピザを注文するかのように、技術のない素人犯罪者(アフィリエイター)が「攻撃したい企業リスト」を渡すだけで、プロが攻撃を代行し、奪った身代金を分け合う…そんな仕組み(エコシステム)が出来上がってしまっています。
これにより、攻撃者の「すそ野」が爆発的に広がり、攻撃回数そのものが激増しているのです。
2. 仮想通貨(暗号資産)の存在
身代金の支払いに、ビットコインなどの「仮想通貨」が使われることも、攻撃を助長しています。
銀行振込と違って、匿名性が高く、お金の流れを追跡(アシがつかない)するのが非常に困難なため、攻撃者にとっては安全に「儲け」を受け取れる手段となっているのです。
3. テレワークの普及
コロナ禍以降、テレワーク(リモートワーク)が急速に普及しましたよね。
これにより、先ほどお話しした「VPN機器」や「リモートデスクトップ」など、外部から社内に接続するための「入口」が急増しました。
急ごしらえで導入したためにセキュリティ設定が甘かったり、管理者の目が届きにくい自宅のパソコンから接続したり…と、攻撃者にとっては狙いやすい「隙」がたくさん生まれてしまったのです。
「儲かる仕組み」ができて、「攻撃のハードル」が下がり、「狙いやすい入口」が増えた…。
これが、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような事件が後を絶たない、根本的な背景なんですね。
感染発覚までのタイムラインと初動対応の分析
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のニュース、私たちが知ったのは10月19日(日)の夕方ごろの報道でした。
実際に、アスクル社内では何が起こっていたのでしょうか?
公式発表(第1報)や報道されている情報から、感染発覚からのタイムラインと、その「初動対応」について整理してみましょう。
【推測されるタイムライン】
- 2025年10月19日(日) 午前(あるいは未明)アスクルのシステムの一部で「異常」が検知されます。セキュリティチームが調査を開始し、これがランサムウェアによるサイバー攻撃であることを確認したとみられます。
- 同日 午前〜午後被害の拡大を防ぐため、感染した可能性のあるシステムをネットワークから緊急で切り離す(遮断する)作業が行われたはずです。この時点で、物流や受注の根幹システムが被害を受けていることが判明し、「受注・出荷の停止」という経営判断が下されたものと推測されます。
- 同日 18:30(夕方)アスクル株式会社が、「ランサムウェア感染によるシステム障害発生のお知らせとお詫び(第1報)」を公式に発表。この中で、ASKUL、LOHACOの受注・出荷停止と、「すでにいただいたご注文についてはご注文キャンセルとさせていただきます」という、利用者にとって最も衝撃的な決定が公表されました。
この「初動対応」を、セキュリティの観点からどう評価できるでしょうか?
【評価できる点:被害拡大防止の徹底】
まず、感染発覚後、ただちに受注・出荷業務という「心臓部」を停止させたことは、非常に迅速かつ勇気ある判断だったと言えます。
中途半端にシステムを動かし続けると、被害がさらに拡大したり、誤った注文データが流れたりする二次被害につながります。
「お客様にご迷惑をかける」と分かった上で、まずは「止血(被害の隔離)」を最優先したことは、初動対応としては正しかったと評価できます。
また、「既存注文の強制キャンセル」という決定も、利用者にとっては辛いものですが、「いつ届くか分からない」という宙ぶらりんな状態を続けるよりは、混乱を最小限に抑えるための苦渋の決断だったのでしょう。
【課題:全容把握と復旧の遅れ】
一方で、丸一日が経過しようとしている20日早朝の時点でも、「復旧のめどは立っていない」「個人情報流出は調査中」という発表しかできていない点は、大きな課題です。
これは、裏を返せば「被害の全容がまだ掴めていない」ことを意味します。
どこまでウイルスが侵入しているのか、そして何より「安全なバックアップデータが生きているのか」という、復旧のキモとなる部分の確認に難航している可能性が非常に高いです。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という事態は、まさに今、アスクルの技術者さんたちが「犯人」と必死に戦っている最中なんですね。私たち利用者は、続報を待つしかありません。
ユーザーはどうするべき?キャンセルや問い合わせの具体的な手順と連絡先
さて、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という非常事態を受けて、私たちユーザーは「今、何をすればいいの?」と不安でいっぱいですよね。
「注文したアレ、どうなるの?」「どこに聞けばいいの?」
そんな疑問に、一つずつお答えしていきます!
注文キャンセルの手順:マイページからの操作方法
「注文した商品が届かないなら、早くキャンセルしなきゃ!」と焦っている方、まず落ち着いてください。
結論から申し上げますと、あなたご自身で「キャンセル操作」をする必要はありません(というか、できません)。
なぜなら、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止を受けて、アスクル株式会社が公式に「すでにいただいたご注文については、大変恐れ入りますがご注文キャンセルとさせていただきます」と発表しているからです。
そう、システム障害で出荷できなくなった「未出荷」の注文は、アスクル側で「すべて強制キャンセル」する、という決定が下されたんです。
「でも、マイページから自分でやりたい!」と思うかもしれませんが、それも不可能な状況です。
ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の攻撃によって、受注システムやWebサイトそのものが正常に機能していません。
公式サイトの情報でも、「お買い物カゴ」や「レジ」、「ご注文内容印刷」などの画面がエラーになると報告されています。
当然、あなたの「注文履歴ページ」も正しく表示されないか、ログインすらできない可能性が非常に高いです。
普段、平時であれば、LOHACOやASKULは「出荷準備に入る前」のわずかな時間だけ、「注文履歴」画面に表示されるキャンセルボタンから手続きができました。
特にLOHACOの「翌日お届け」などを選ぶと、注文後すぐにキャンセルできなくなる、というのはご存知の方も多いと思います。
ですが、今は「平時」ではありません。「非常事態」です。
ですから、あなたが今すべきことは「マイページに何度もアクセスしようと試みること」ではなく、「注文は自動的にキャンセル扱いになる」と理解し、後述する「返金」に関する情報や、公式からの続報を待つことです。
ただし、もし障害発生前に「発送完了メール」がすでに届いている商品については、アスクルの倉庫から配送業者へ渡っている可能性があります。その場合はキャンセル扱いにならず、そのまま届くか、配送の途中で止まっているかのどちらかになります。これについても、個別の追跡が困難になっている可能性が高く、やはり続報を待つしかありません。
問い合わせ先一覧:電話・メール・チャットの連絡情報
「キャンセルになるのはわかったけど、やっぱり不安だから問い合わせしたい!」
そのお気持ち、痛いほどわかります。
ですが、どうか冷静にお考えください。
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止は、日本全国の法人ユーザー(ASKUL)と個人ユーザー(LOHACO)の物流がストップするという、前代未聞の大規模障害です。
今この瞬間、アスクルやLOHACOのお客様サービスデスクには、想像を絶する数の電話やメールが殺到しているはずです。
結論として、電話、メール、チャット、いずれの窓口も完全にパンク状態であり、繋がる可能性は限りなくゼロに近いと覚悟してください。
「LOHACOお客様サービスデスク」や「ASKULお客様サービスデスク」といった平時の窓口はもちろん存在します。
ですが、仮に運良く電話が繋がったとしても、オペレーターさんができることは何でしょうか?
オペレーターさんが見る「お客様の注文データ」や「システム」そのものがランサムウェアにやられて停止しているのです。
「あなたの注文が今どうなっているか」を調べることすらできず、「申し訳ございません、現在システム障害で復旧のめどは立っておりません」「公式サイトのお知らせをご覧ください」という回答しかできない可能性が非常に高いです。
問い合わせ窓口も、今回の被害者なのです。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の被害を受けている今、私たちユーザーが取るべき最も賢明な行動は、個別に問い合わせて窓口の混乱に拍車をかけることではありません。
アスクルやLOHACOの公式サイトのトップページに掲示される「お知らせ」や、信頼できるニュース速報を、冷静に待つこと。
これが、一番確実で、一番早く正しい情報を得る方法です。
不安な気持ちを抑えて、今は「待つ」ことに徹しましょう。
返金処理の流れと所要時間
「注文が強制キャンセルになるのはわかった。じゃあ、払ったお金はどうなるの!?」
これ、一番大事なことですよね!
ご安心ください。アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止によって強制キャンセルとなった注文については、支払った代金は必ず返金処理されます。
ただし!
ランサムウェア攻撃で決済システムや受注システムそのものがダウンしているため、その返金処理が完了するまでには、通常では考えられないほどの時間がかかる可能性が非常に高いです。
数日どころか、数週間、あるいは1ヶ月以上かかるケースも覚悟しておいた方がよいかもしれません。
返金の流れは、あなたの支払い方法によって異なります。
1. クレジットカード決済の場合
これが一番多いパターンだと思います。平時の返品であれば、カード会社経由で返金(請求の取り消し、またはマイナス計上)されます。今回も、アスクル側のシステムが復旧しだい、カード決済の「キャンセル(取り消し)」処理が行われるはずです。すでにカード会社の締め日を過ぎていた場合は、一度請求が上がってしまい、翌月以降の明細で「マイナス(返金)」として処理される可能性が高いです。
2. デビットカード・プリペイドカードの場合
これが一番注意が必要です。デビットカードなどは、注文と同時にあなたの銀行口座から「即時引き落とし」されていますよね。アスクルが返金処理(キャンセル処理)を行うまで、そのお金は戻ってきません。カード会社にもよりますが、返金が実行されるまで1ヶ月~2ヶ月近くかかることも珍しくありません。口座の残高が減ったままになる期間が長引くことを覚悟してください。
3. 掛け払い(法人向けASKUL)の場合
法人向けのASKULで「月末締め・翌月払い」などの掛け払いを利用していた場合、今回の強制キャンセル分は、請求データそのものから削除される形で処理されるはずです。ただし、システムの復旧タイミングによっては、一度誤った金額で請求書が発行されてしまう混乱も考えられます。月末の請求書は、いつも以上に注意深くチェックする必要がありそうです。
いずれにせよ、システムが復旧しないことには返金処理も始まりません。今は辛抱強く待つしかありませんね。
【参照】
代替購入の推奨:Amazonや楽天への切り替え方法
「アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止」の復旧、いつになるか分かりません。
公式発表でも「復旧のめどは立っていない」とされています。
「明日には直るかも…」と待ち続けるのは、特に業務で備品を必要とする法人にとっても、日用品が切れた個人にとっても、非常にリスクが高いです。
結論として、必要なものは、今すぐ他のサービスに切り替えて購入することを強く、強く推奨します!
幸い、私たちには多くの選択肢があります。
【法人(ASKUL・ソロエルアリーナ)ユーザー向け】
オフィスのコピー用紙、トナー、お茶、文房具…「明日ないと困る!」ものだらけですよね。
ASKULの代替として最も強力なのは、やはり「Amazonビジネス」です。
これは法人・個人事業主向けのAmazonで、私たち個人が使うAmazonとほぼ同じ使い勝手ながら、「請求書払い(掛け払い)」に対応していたり、法人向けの価格が設定されていたり、購入を承認制にできたりと、ビジネスユースに最適化されています。無料アカウントをすぐに作れますよ。
また、もともとASKULの強力なライバルである、「カウネット」(コクヨグループ)や「たのめーる」(大塚商会)も、もちろん通常通り営業しています。この機会に、他のサービスに乗り換える(あるいは併用する)ことを検討する良い機会かもしれません。
【個人(LOHACO)ユーザー向け】
LOHACOで日用品やお米、飲み物、コスメ、医薬品などをまとめて買っていた方!
代替先は豊富にあります。
1. Amazon / 楽天市場
言わずと知れた2大巨頭です。LOHACOで買えていた商品のほとんどは、Amazonや楽天でも揃います。「あす楽」や「プライム配送」などで、緊急で必要なものも手に入りやすいですね。
2. ネットスーパー(イオン、イトーヨーカドーなど)
これが意外と強力な穴場です! お米や飲み物、トイレットペーパーといった重い・かさばる日用品はもちろん、LOHACOでは買えなかった「生鮮食品(野菜、肉、魚)」まで一緒に注文でき、自宅まで届けてくれます。即日~翌日配送に対応しているエリアも多いです。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の復旧を待つ間は、これらのサービスを賢く利用して生活と業務を守りましょう!
被害補償の請求方法と注意点
「注文がキャンセルになった!」「仕事の備品が届かなくて業務に支障が出た!」「高くても別の店で買うしかなかった!」
…こうした「被害」について、アスクルに「補償」を請求したい、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
まず、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止に関して、2025年10月20日(月)の時点で、アスクル株式会社から発表されている対応は、
「(強制キャンセルした注文の)代金を返金する」
という点のみです。それ以外の「被害補償」については、一切言及されていません。
ここで冷静に考えなければいけないのは、「補償」の範囲です。
【補償されるもの(=返金)】
・すでに支払ったが、商品が届かなくなった注文の代金。
これは「直接的な損害」であり、当然返金されます。
【補償されない可能性が“極めて”高いもの】
・「LOHACOで買えば1,000円だったのに、近所のスーパーで1,200円で買うしかなかった。差額の200円を補償しろ」
・「ASKULからトナーが届かず、プリンターが使えず、契約書が印刷できなかった。この業務上の損害(逸失利益)を補償しろ」
これらは「間接的な損害」と呼ばれます。
ASKULやLOHACOを利用する際には、必ず「利用規約」に同意しているはずですが、こうした規約には、通常、「システム障害や不測の事態によって生じたいかなる間接的損害についても、当社は責任を負いません」といった旨の免責条項が必ず記載されています。
したがって、こうした間接的な損害の補償を請求しても、法的に認められる可能性は非常に低いです。
【今後、あり得る「補償」(お詫び)】
ただし、今後の調査の進展、特に「個人情報が大規模に流出してしまった」という事実が万が一確定した場合には、話は別です。
その場合は、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の迷惑と、個人情報流出に対する「お詫び」として、全ユーザー(あるいは流出対象者)に対して一律で「500円分の金券」や「1,000円分のポイント」などが配布される…といった対応が取られる可能性はあります。(あくまで過去の他社事例からの推測です)
しかし、現時点で私たちが「補償しろ!」と請求する具体的な方法はありません。まずはシステムの復旧と、支払った代金の「返金」が確実に行われることを見守りましょう。
セキュリティ専門家の意見:今回の被害から学ぶ教訓と対策
セキュリティ専門家の意見:今回の被害から学ぶ教訓と対策
さて、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という衝撃的なニュース。私たち利用者は「早く復旧して!」と願うばかりですが、セキュリティの専門家たちは、この事件をまったく違う、もっと厳しい目で見ています。
彼らは「なぜ被害が起きたのか」だけでなく、「なぜこれほどまでに復旧が遅れているのか」という点を、最大の焦点として分析しているんです。
このセクションでは、専門家たちが指摘する「本当の原因」と、私たち(特に企業)が学ぶべき「未来のための教訓」について、一緒に考えていきましょう。
専門家が指摘するアスクル被害の根本原因
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という事態について、専門家たちが指摘する「根本原因」は、多くの方が想像するものと少し違うかもしれません。
もちろん、ウイルスに「侵入された」ことは第一の問題です。
しかし、現代のサイバー攻撃はあまりにも巧妙化しており、専門家の間では「侵入を100%防ぐことは不可能」というのが、もはや常識なんです。
では、本当の根本原因はどこにあるのか?
それは、「侵入された後(・・・・・)の対応、すなわち被害軽減(レジリエンス)の仕組みが機能しなかったこと」にある、と多くの専門家は見ています。
今回の被害がここまで拡大し、ついには「復旧のめどが立たない」という最悪の事態に陥ってしまった背景には、大きく分けて3つの「失敗」が推測されます。
1. 「検知」の遅れ
攻撃者は、システムに侵入してすぐにランサムウェア(身代金要求型ウイルス)を起動するわけではありません。
まず社内ネットワークに潜伏し、数日、時には数週間かけて、じっくりと「どこに重要データがあるか」「バックアップはどこだ」と偵察活動を行います。
アスクルが「異常を検知」したのが10月19日(日)の午前中とされていますが、実際に侵入されたのは、それよりもずっと前だった可能性が非常に高いです。
この「潜伏期間中」に攻撃者の怪しい動きを検知できなかったこと、特に監視体制が手薄になりがちな休日を狙われた(あるいは休日に発覚が遅れた)ことが、被害を致命的にした第一の原因と考えられます。
2. 「横展開」の許容
攻撃者は侵入後、一台のパソコンから次へと乗り移り、最終的にシステム全体を支配しようとします。これを「横展開」と呼びます。
今回の被害は、コピー用紙を売るサイトだけでなく、LOHACOの受注システム、そして物流の根幹まで、すべてが停止しています。
これは、攻撃者がシステムの中枢まで自由に動き回り、会社の心臓部を乗っ取ることを許してしまった、ということに他なりません。
本来であれば、システムとシステムの間には厳重な「壁」(専門用語でセグメンテーションと言います)があり、万が一侵入されても被害を一部門に限定する設計になっているべきでした。
この「壁」が甘かったのではないか、というのが専門家の見立てです。
3. 「復旧」の失敗(バックアップの壊滅)
そして、これが最大の原因と目されているものです。
なぜ「復旧のめどが立たない」のか?
それは、データを元に戻すための「バックアップデータ」までもが、攻撃者によって破壊されたか、一緒に暗号化されてしまった可能性が極めて高いからです。
攻撃者はプロです。本丸を攻撃する前に、必ず「バックアップサーバー」を探し出し、先に潰しにかかります。
安全なバックアップさえ生きていれば、システムをクリーンアップし、データを戻せば、数日中には業務再開できるはずなのです。
それができないということは、アスクルは「身代金を払うか、ゼロからシステムを作り直すか」という、最悪の二択を迫られている状況なのかもしれません。
専門家たちは、侵入されたこと自体よりも、この「復旧戦略の甘さ」こそが、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という大惨事を招いた根本原因だと厳しく指摘しているのです。
企業向けランサムウェア対策のベストプラクティス5選
「じゃあ、どうすればアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような事態を防げたの?」
今回の事件は、すべての企業にとって他人事ではありません。
専門家が推奨する、現代のランサムウェア(身代金要求型ウイルス)対策は、もはや「ウイルス対策ソフトを入れる」といった単純なレベルの話ではないんです。
「侵入前(入口)」「侵入後(内部)」「被害後(出口=復旧)」の3段階で考える必要があり、特に重要な「ベストプラクティス(最善の手法)」を5つ、ご紹介します。
1. 脆弱性(ぜいじゃくせい)管理の徹底【入口対策】
まず、基本中の基本ですが、これができていない企業が驚くほど多いです。
「脆弱性」とは、ソフトウェアや機器の「セキュリティ上の穴」のこと。
特に、社員が外から社内に入るための「VPN機器」や、外部に公開しているサーバーの穴を放置していると、攻撃者はそこから堂々と侵入してきます。
メーカーから修正プログラム(パッチ)が配布されたら、即座に適用すること。当たり前のようですが、これが第一の砦です。
2. 多要素認証(MFA)の全面導入【内部対策】
もはや「常識」です。IDとパスワードだけでログインできるシステムは、裸で歩いているようなもの。
重要なシステム(特にVPNや管理者権限)にアクセスする際は、ID・パスワードに加えて、必ず「スマートフォンアプリの確認コード」や「指紋認証」などを要求する「多要素認証(MFA = Multi-Factor Authentication)」を必須にすべきです。
もし攻撃者にパスワードが盗まれても、この第二の関門が侵入を防いでくれます。
3. EDR(Endpoint Detection and Response)の導入【内部対策】
これが現代のセキュリティの主役です。
従来のウイルス対策ソフト(アンチウイルス)は、「過去に見つかったウイルス」しか検知できません。
「EDR」は違います。EDRは「侵入されること」を前提に、パソコンやサーバーの「いつもと違う怪しい動き」を監視し、検知する仕組みです。
例えば、「経理部のAさんのPCが、夜中に人事部のサーバーにアクセスし、データを暗号化し始めた」といった異常を即座に検知し、そのPCを自動でネットワークから切り離す、といった対応が可能です。
4. ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行【内部対策】
「社内ネットワークは安全だ」という考え方を今すぐ捨てるべき、という考え方です。
「ゼロトラスト(何も信用しない)」とは、社内の通信であっても、すべてのアクセスを疑い、厳しく認証・認可すること。
システム間の「壁」(セグメンテーション)を細かく作り、万が一アスクルのように侵入されても、被害をその一部門だけに閉じ込め、受注・出荷システムのような中枢まで「横展開」させないための設計思想です。
5. バックアップの「3-2-1ルール」と「不変性」【出口対策】
そして、これが最後の命綱です。次の見出しで詳しく解説しますが、ランサムウェア対策とは、突き詰めれば「いかに安全なバックアップを守り抜くか」の戦いでもあるのです。
これらの対策にはコストがかかりますが、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止が引き起こした損害(売上停止、顧客離れ、信用の失墜)を考えれば、もはや「投資」ではなく「必須コスト」であることがわかりますね。
バックアップシステムの重要性と復旧戦略
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止の騒動で、私たちが学ぶべき最大の教訓。
それは、「バックアップシステムこそが、企業の最後の命綱である」という、揺るぎない事実です。
なぜ専門家たちが「アスクルのバックアップは壊滅したのでは?」と推測するのか。
それは、アスクルが「復旧のめどが立たない」と発表し続けているからです。
もし、攻撃を受けても、無傷で安全なバックアップデータさえ残っていれば、どうなるでしょう?
システムをクリーンアップ(掃除)し、安全なデータを元に戻す(リストアする)ことで、たとえ数日はかかったとしても、「○月○日ごろに再開見込みです」という発表ができるはずなんです。
それが言えないということは、「元に戻すべきデータそのものが無い(または破壊された)」という、絶望的な状況に陥っている可能性を強く示唆しています。
ランサムウェア攻撃者は、もはや素人ではありません。彼らはシステムに侵入した後、データを暗号化する前に、まず何よりも先に「バックアップサーバー」を探し出し、徹底的に破壊します。
企業に「復旧」という選択肢を奪い、「身代金を払う」しか道を残させないためです。
では、どうすればバックアップを守れたのでしょうか?
専門家が口を揃えて言うのが、「バックアップの3-2-1ルール」と「イミュータビリティ(不変性)」です。
「3-2-1ルール」とは、
・データは常に「3」つコピーを持つ(オリジナル+バックアップ2つ)
・「2」種類の異なるメディア(媒体)に保存する(例:ハードディスクとクラウド)
・そのうち「1」つは、必ず「オフライン」または「オフサイト(遠隔地)」に保管する
という黄金律です。
特に「1」のオフライン(ネットワークから物理的に切り離す)が重要で、これさえあれば攻撃者は手が出せません。
そして、最近のトレンドが「イミュータブル・バックアップ」です。
「イミュータブル」とは「変更・削除 不可能」という意味。
一度バックアップとして保存したデータは、設定した期間(例えば14日間)、絶対に誰も(たとえ社長でも、システム管理者でも、侵入した攻撃者でも)削除したり暗号化したりできない、という最強の仕組みです。
これさえ導入していれば、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような事態になっても、確実にデータを復旧し、数日中には業務を再開できたはずなのです。
バックアップは、「取っておけば安心」ではありません。「いかに攻撃者から守り抜き、確実に復旧できるか」という戦略(復旧戦略)こそが、企業の生死を分けるのです。
社員教育のポイント:フィッシング回避トレーニング
どんなに何億円もする最新のセキュリティ機器を導入しても、アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような大事件の「最初のきっかけ」は、たった一人の社員が、たった一通のメールをクリックしたことだった…というのは、本当によくある話なんです。
攻撃者は、高い壁(システム)を乗り越えるよりも、人間を騙す(ソーシャルエンジニアリング)方がずっと簡単だと知っています。
だからこそ、専門家は「社員教育」、特に「フィッシングメール」を見抜く訓練が、今もなお最も重要で、最もコストパフォーマンスの高い対策だと断言します。
「うちは大丈夫だよ」と思っている企業ほど危険です。
最近のフィッシングメールは、昔のような「カタコトの日本語」ではありません。
実在する取引先や、ASKULのような配送業者、あるいは税務署や銀行を完璧に装い、「【緊急】請求書の内容をご確認ください」「アカウントがロックされました」といった、思わず焦ってクリックしてしまう件名で送られてきます。
私たちが日常的に身につけるべき「回避ポイント」は4つあります。
1. 「差出人」を疑う
メールに表示されている「名前」(例:アスクル株式会社)は、簡単に偽装できます。必ず、メールアドレスの「@」より後ろの部分(ドメイン)を見てください。そこが askul.co.jp ではなく、askul.co-jp.xyz や askul.security-info.com のように、微妙に違っていたら100%偽物です。
2. 「緊急」「パスワード」の言葉に焦らない
攻撃者は、あなたを「焦らせる」ことで正常な判断力を奪おうとします。「至急」「重要」「警告」といった言葉や、「パスワードを入力してください」「情報を更新してください」と個人情報を入力させようとするメールは、まず詐欺だと疑ってください。
3. リンクは「クリックせず」に「確認」する
本文中の「詳細はこちら」といったリンクも、すぐにクリックしてはいけません。
パソコンであれば、リンクの上にそっとマウスカーソルを乗せてみてください(ホバー)。画面の左下などに、「本当の飛び先URL」が表示されます。そのURLが、本文の内容と関係ない怪しいものであれば、絶対クリックしてはいけません。
4. 添付ファイルは「開かない」
「請求書.zip」「発注書.xlsx」といった添付ファイルは、最も危険です。特に、それがパスワード付きZIPファイルだった場合、ウイルス対策ソフトをすり抜けるためにわざとやっている可能性が高いです。
心当たりがない添付ファイルは、業務上必要であっても、まず送信元に電話などで「本当に送りましたか?」と確認するクセをつけるべきです。
こうした知識は、一度研修で聞いただけでは忘れてしまいます。企業は、定期的に「標的型攻撃メール訓練」といって、社員に“偽物のフィッシングメール”を抜き打ちで送り、誰がクリックしてしまうかをテストし、繰り返し意識付けを行うことが不可欠なのです。
今後のトレンド:AI活用のセキュリティ強化術
「人間がミスをするのは仕方ない。じゃあ、機械でなんとかならないの?」
その通りです。今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような事件を防ぐ切り札として、今、セキュリティ業界の注目を一身に集めているのが、「AI(人工知能)」の活用です。
ただし、残念ながら「悪い攻撃者」たちも、すでにAIを悪用し始めています。
AIを使って、より巧妙で本物そっくりなフィッシングメールの文章を自動生成したり、AIにプログラムの脆弱性(穴)を自動で探させたりしています。
これからは、「AI vs AI」のセキュリティ戦争になっていくのです。
では、私たち「守る側」は、AIをどう活用していくのでしょうか?
1. AIによる「異常検知」
これが本命です。
まず、AIに「あなたの会社の“平常時”の動き」をすべて学習させます。
「Aさんはだいたい平日の9時~18時に、経理サーバーにアクセスする」「B部長は、海外出張中はこの国のIPアドレスからアクセスする」といったパターンです。
すると、AIは24時間365日、システム全体を監視し続けます。
そして、万が一、アスクルのように攻撃者が侵入し、「AさんのIDが、日曜の深夜3時に、今までアクセスしたことのない人事サーバーのデータを暗号化し始めた!」といった「“平常時”と違う動き」を検知した瞬間、AIが「これは異常だ!」と判断します。
2. AIによる「即時対応(SOAR)」
AIは、ただアラートを鳴らすだけではありません。
「SOAR(ソアー)」と呼ばれる仕組みと連携し、異常を検知したら、人間が駆けつけるよりも早く、数秒で「対応」まで自動で実行します。
例えば、先ほどの異常を検知したら、即座に「Aさんのアカウントを強制ロックする」「AさんのPCをネットワークから遮断する」といった対処を行い、ランサムウェアが横展開する前に被害を食い止めることができます。
3. AIによる「メール・フィルタリング」
社員教育はもちろん重要ですが、AIは「入口」でも活躍します。
送られてくるメールの文面、送信元の評判、リンク先などをAIが瞬時に分析し、「このメールは99.8%フィッシング詐欺です」と判定し、社員の受信箱に届く前に隔離・ブロックする精度が、日々向上しています。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような悲劇を繰り返さないため、これからの企業セキュリティは、AIの力を借りて、人間の目では追いきれない「怪しい動き」をいかに早く見つけ、いかに早く止めるか、という戦いになっていくんですね。
LOHACO利用者の声:「日用品が買えない」緊急時の代替サービスは?
Twitter(X)上の利用者反応:不便さと怒りの声まとめ
さて、今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のニュース。公式サイトが「システム障害」と発表した後、SNS、特にTwitter(X)上は、まさに「阿鼻叫喚」といった状態になりました。
そりゃそうですよね…!
まず、個人向けのLOHACO(ロハコ)ユーザーからは、「週末のまとめ買いが全部パーになった!」という悲鳴が相次ぎました。
「明日届くはずのトイレットペーパー、どうしてくれるの!」といった日用品の枯渇を心配する声や、「赤ちゃんのオムツとおしりふきのストック、LOHACO頼りだったのに…」という、子育て中のママさん・パパさんたちの切実な叫びが溢れかえっていました。
日曜日というタイミングも最悪で、「今注文すれば月曜に届く」と計算していた方々の生活が、直撃を受けた形です。
中には、「LOHACO限定デザインのボックスティッシュ、やっと買ったのにキャンセルされた…ショックすぎる」といった、LOHACOならではの価値を楽しみにしていた方の落胆の声も目立ちます。
そして、もう一方のASKUL(アスクル)を使っている法人・個人事業主の方々は、文字通り「死活問題」だと、不便さを通り越して怒りの声を上げています。
「月曜朝イチで使うコピー用紙が届かない!仕事にならない!」という事務担当者さんの悲鳴や、「インクもトナーも全部ASKULで管理してた…どうしよう」といった、業務停止の危機を訴える声が多数見られました。
さらに深刻なのは、「アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止」という原因が報道されてからです。
「ランサムウェアって…うちの個人情報やカード情報は大丈夫なの!?」と、システムの不便さよりも個人情報流出の可能性に恐怖を感じている声も多く、「復旧より先に、まず情報流出の有無をハッキリさせて!」という当然の要求が飛び交っています。
「早く復旧して」という願いと共に、「なぜこんなことに」「補償は?」「もうLOHACO依存はやめようかな…」といった怒りや不安、そして諦めの声が渦巻いているのが、SNS上のリアルな反応ですね…。
日用品購入の代替サイトおすすめ3選:特徴比較
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止で、特にLOHACO(ロハコ)をメインに使っていた方々は、「これからどこで日用品を買えばいいの?」と路頭に迷ってしまいますよね。
LOHACOといえば、おしゃれな限定デザインのパッケージや、無印良品の商品が一緒に買える便利さ、Yahoo!ショッピング経由でのPayPayポイントの貯まりやすさなど、独特の魅力がありました。
あの便利さを100%代替するのは難しいかもしれませんが、復旧を待つ間の「ピンチヒッター」として、非常に強力な代替サイトを3つ、特徴とともに比較検討してみましょう!
LOHACOの最大の強みは「日用品・コスメ・医薬品・食品まで、重くてかさばるものを一度にまとめて届けてくれる」ことでした。この点をカバーできるのは、やはり大手ECサイト、そして「あの」サービスです。
【LOHACO代替 日用品購入サイト比較】
| 代替サイト | 最大の特徴 | メリット (強み) | デメリット (弱み) |
|---|---|---|---|
| 1. Amazon (アマゾン) | 圧倒的な品揃えと配送スピード | ・プライム会員なら送料無料ですぐ届く
・「定期おトク便」でストック管理が楽 ・LOHACOで扱っていない商品もほぼ見つかる |
・サイトが雑然としていて見づらいことがある
・マーケットプレイス(転売業者)に注意が必要 ・おしゃれな限定デザインなどは無い |
| 2. 楽天市場 (Rakuten) | 楽天ポイントの圧倒的な還元率 | ・「Rakuten24」がLOHACOの代替として強力
・SPUやお買い物マラソンでポイントが爆発的に貯まる ・楽天経済圏のユーザーには最適 |
・ショップごとに送料が異なるのが面倒
・「あす楽」対応か確認が必要 ・ポイントを意識しないと割高になることも |
| 3. ネットスーパー
(イオン, イトーヨーカドー等) |
生鮮食品(野菜・肉・魚)も一緒に買える | ・LOHACOでは買えない生鮮食品もワンストップ
・最短当日配送など、配送が非常に速い ・PB商品(トップバリュ等)が安くて優秀 |
・日用品やコスメの「品揃え」はLOHACOに劣る
・配送料が比較的高い場合がある ・人気の配送枠はすぐ埋まってしまう |
どうでしょうか?
「とにかく早く、LOHACOと同じ感覚で日用品だけ欲しい!」という方は、Amazonのプライム配送やRakuten24が有力な候補になりますね。LOHACOで貯めていたPayPayポイントのことは一旦忘れて、緊急避難しましょう。
一方で、「どうせ届けてもらうなら、今日の夕飯の材料(野菜やお肉)も一緒に買ってしまいたい!」という方は、この機会にネットスーパーを試してみるのが一番賢い選択かもしれません。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止がいつまで続くか分かりません。まずはこれらの代替サイトで、当面の生活必需品を確保してくださいね!
緊急時の在庫確認方法:他のECサイトの活用術
「LOHACOがダメだからAmazonに行ったら、もうトイレットペーパーが売り切れてた!」
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止のような大規模な物流停止が起こると、次に発生するのがこれです。
そう、代替サイトへの「パニック買い」による連鎖的な品切れです。
特にトイレットペーパー、ティッシュ、お米、水、オムツといった必需品は、あっという間にAmazonや楽天でも「在庫なし」になってしまいます。
そんな「緊急時」に、欲しい商品の在庫を賢く見つけるための「活用術」を伝授します!
まず、Amazonや楽天で「在庫なし」と表示されても、諦めずに「お気に入り」や「ほしい物リスト」に入れておくことです。
検索結果のページでは「在庫なし」と表示されていても、リストのページをこまめにリロード(再読み込み)すると、キャンセル分の在庫が復活したり、ごく少量の入荷が反映されたりすることがよくあります。検索から探すよりも早く在庫の復活をキャッチできる裏ワザです。
次に、「総合ECサイト」だけでなく「専門ECサイト」を狙うことです。
例えば、医薬品や化粧品が欲しいなら、Amazonや楽天だけでなく、「マツモトキヨシ オンラインストア」や「ココカラファイン」といったドラッグストア独自のECサイトを確認します。
法人のASKULでインクやトナーが買えなくなったなら、家電量販店のECサイト、特に「https://www.yodobashi.com/」や「https://www.google.com/search?q=%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9.com」をチェックしましょう。
これら専門サイトは、LOHACOやAmazonとはまったく別の在庫(倉庫)を持っているため、パニック買いの影響を受けていない可能性が高いのです。
最後に、「メーカー公式サイト」の直販ストアを訪れることです。
LOHACOで特定のコスメを買っていたなら、その化粧品メーカー(例:資生堂、コーセーなど)の公式サイトを訪れてみてください。メーカー自身が運営するオンラインショップは、小売店(LOHACOなど)への卸しとは別に、「直販用」の在庫を確保していることがほとんどです。
みんなが殺到するメジャーな場所を避け、在庫が分散している「専門サイト」や「公式サイト」を狙う。これが緊急時の鉄則ですね!
【参照】
LOHACO再開までの生活Tips:ストック管理のコツ
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止で、「あ、うち、トイレットペーパーの在庫があと1個しかない…!」と真っ青になった方、多いのではないでしょうか。
LOHACOやASKULの「注文したら明日届く」という超高速物流は、私たちの生活を劇的に便利にしてくれました。
しかし、その便利さゆえに、私たちは「家の在庫(ストック)をゼロに近づける」クセがついてしまったのかもしれません。
このランサムウェア被害は、私たちに「一箇所に依存するリスク」と「ストック管理の重要性」を痛感させる、強烈な教訓となりました。
LOHACOが再開するまでの間、そして再開した後も、私たちが実践すべき「生活防衛Tips」は、ずばり「在庫ゼロ」を目指さないことです。
最も簡単で強力なコツは、「使っているもの1つ、ストック1つ」(ワン・イン・ストック)のルールを徹底することです。
例えば、シャンプーの詰め替え用。今使っているボトルの他に、最低1つは新品のストックを必ず置いておきます。
そして、ストックしていたその「最後の一つ」を開封した瞬間(・・・・・)、それが「次の分を発注する合図」です。
今使っているボトルが空になってから注文するのでは、今回のような物流停止が起きた瞬間に詰んでしまいます。
トイレットペーパーなら、「最後の1パック」を開封したら、次のパックを注文する。
この「合図」さえ守れば、手元には常に1パック+使いかけの在庫が確保され、数週間は余裕で耐えられるようになります。
さらに、購入先を分散させておくことも重要です。
「日用品は全部LOHACO!」と決めてしまうと、今回のようにアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止となった場合に、すべてのライフラインが同時に断たれます。
「紙類と洗剤はLOHACO」「重い飲み物と米はAmazon」「コスメは楽天」というように、意図的に購入先を分散させておく(リスク分散)ことで、どれか一つが停止しても、他のルートでカバーできる体制を築いておきたいですね。
利用者アンケート結果:被害の影響度と満足度調査
今回のアスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という事態について、まだ障害が発生したばかり(2025年10月20日時点)であるため、公式な「利用者アンケート」や「満足度調査」の結果は、もちろんまだ存在しません。
しかし、先ほどまとめたTwitter(X)上での利用者のリアルな反応を分析するだけでも、もし今アンケート調査を行ったとしたら、非常に厳しい結果が出ることは火を見るより明らかです。
仮にアンケートを実施した場合、以下のような結果が予測されます。
まず、「今回の障害による被害の影響度」について。
ASKUL法人ユーザー、LOHACO個人ユーザーともに、「非常に深刻な影響があった」と回答する利用者が、おそらく8割を超えるのではないでしょうか。
その理由として、法人は「業務に必要な備品が調達できず、仕事が止まったから」、個人は「生活必需品(オムツ、ペーパー類)が手に入らず、生活に支障が出たから」という、極めて深刻な回答が集中すると考えられます。
次に、「アスクル社の対応への不満点」について。
最も多い不満は、もちろん「復旧のめどが立たないこと」への強い不安と苛立ちでしょう。
次いで、「ランサムウェア感染」と聞き、「個人情報やカード情報が流出したのかどうか、調査中でハッキリしないこと」への恐怖と不満が続くと予想されます。
さらに、「すでに注文し、届くのを楽しみにしていた商品が一方的に『強制キャンセル』された」という対応への不満も、満足度を大きく引き下げる要因となっているはずです。
そして、最も注目すべきは「今後の利用意向」です。
「今後もLOHACO / ASKULをメインの購入先として利用し続けますか?」という質問に対し、おそらく「利用を続けたいが、今後は他社(Amazonや楽天など)と併用し、依存度を下げる」という回答が大多数を占めるのではないでしょうか。
アスクル・LOHACO、ランサムウェア感染で受注・出荷停止という今回の事件は、便利さの裏にあった「一極集中リスク」を利用者が痛感するきっかけとなりました。アスクル社が失った「信頼」の回復には、システムの復旧以上に、長い時間がかかることになりそうです。
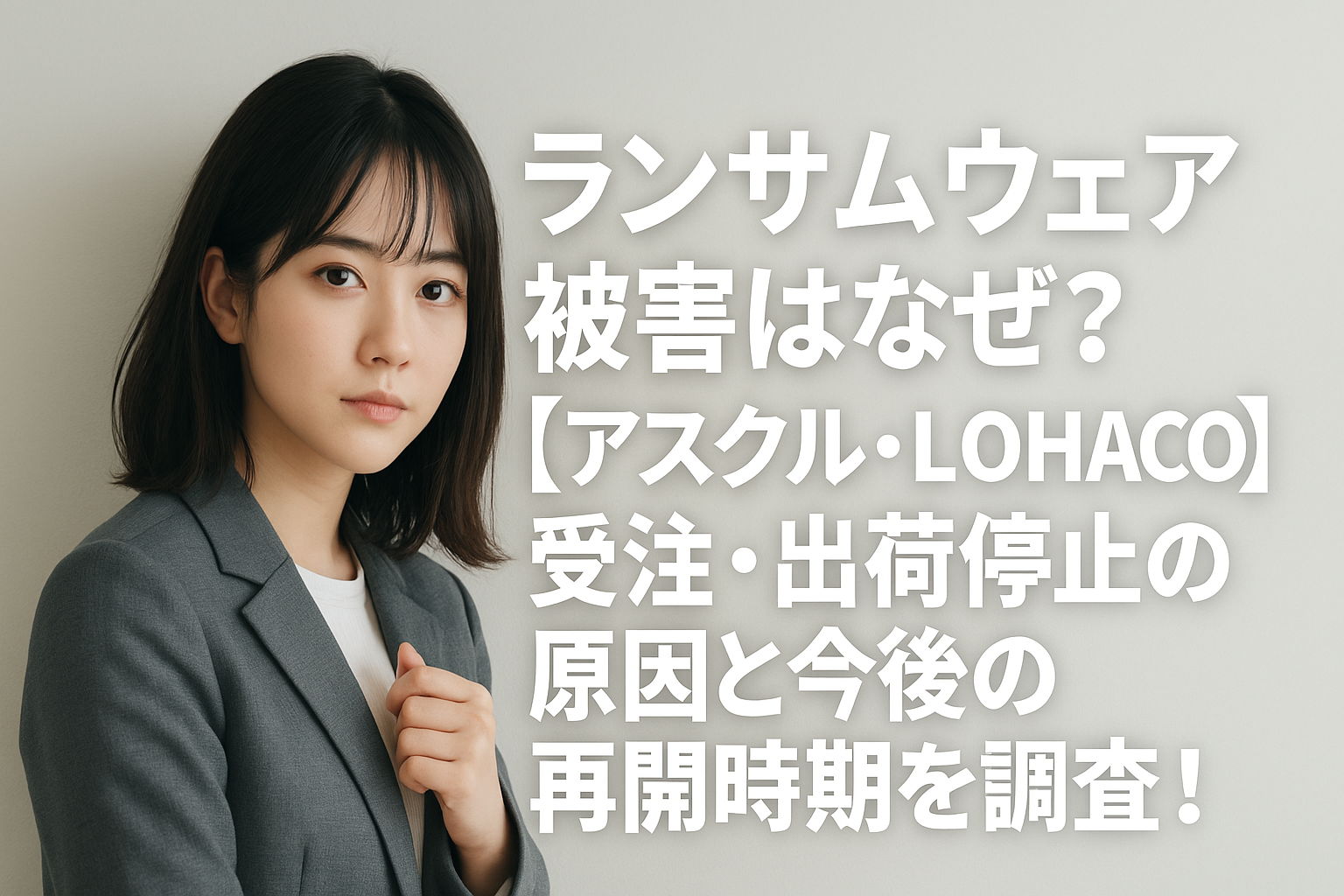
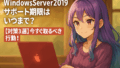

コメント